夕方に眠くなる原因って?意識が飛ぶくらい眠気がひどいときの対処法を解説
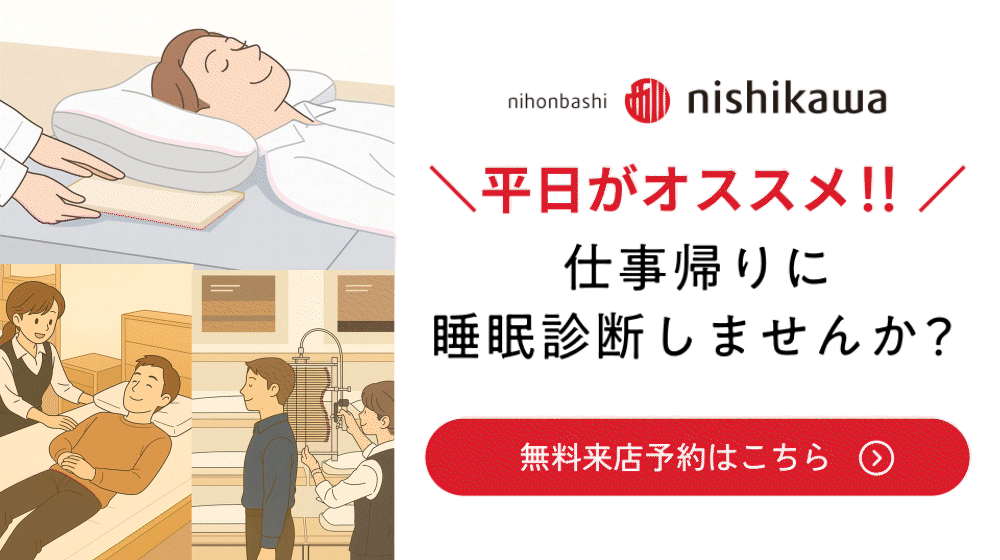
夕方になると突然襲ってくる強烈な眠気。仕事中や勉強中に意識が朦朧として、気がつくと船を漕いでいた…そんな経験はありませんか?この時間帯の眠気は単なる疲れではなく、私たちの体内時計や生活リズムと深く関わっています。
夕方に感じる眠気は「アフタヌーンディップ」と呼ばれ、実は多くの人が経験する自然な現象です。しかし、その眠気があまりにも強く、日常生活に支障をきたすほどであれば、適切な対策が必要になります。
この記事では、夕方の眠気が起こるメカニズムから、意識が飛ぶほどの強い眠気への実践的な対処法まで、科学的根拠に基づいて詳しく解説していきます。眠気に悩まされることなく、午後の時間を有効活用できるようになりましょう。
夕方に眠くなるのはなぜ?主な原因6つ

夕方に眠くなる主な原因は以下の6つが考えられます。これらの要因が複合的に作用し、夕方に眠気を感じることが多いと考えられます。
サーカディアンリズム(概日リズム)によるもの
サーカディアンリズム(概日リズム)は、私たちの体に備わった約24時間周期の体内時計のことで、睡眠と覚醒のパターンを制御する重要な仕組みです。この体内時計は脳の視交叉上核という部分が司令塔となり、光の刺激によって調整されています。興味深いことに、現在では体の全ての細胞に時計機能があることが分かっており、全身が協調して生体リズムを維持しています。
サーカディアンリズムによる眠気は一日の中で特徴的な波を描きます。昼過ぎに小さな眠気の山が現れ、その後一度眠気は軽減されるものの、夕方に再び小さな山が訪れます。これが多くの人が午後3時から5時頃に感じる「アフタヌーンディップ」の正体です。
その後、就寝時間に向けて大きな眠気の山が形成され、朝まで続きます。このリズムは外部環境に関係なく体内で自動的に生成されるため、たとえ意識的に眠気を抑えようとしても、生理的な眠気として現れてしまうのです。

睡眠負債の蓄積によるもの
睡眠負債の蓄積は、夕方に強い眠気を感じる主要な原因の一つです。睡眠負債とは、慢性的な睡眠不足の状態が続き、その負債が蓄積されて心身へ支障をきたしている状態を指します。例えば、必要な睡眠時間が7時間の人が5時間しか眠れていない場合、毎日2時間ずつ不足分が蓄積され、わずか10日間で20時間もの睡眠不足が積み重なることになります。
この睡眠負債は体内で静かに蓄積されていき、多くの人が自覚しないまま心身に深刻な影響を与えます。睡眠不足が続くと日中のパフォーマンスに大きな影響を与えます。体は本来必要な休息時間を確保できずにいるため、午後から夕方にかけて強烈な眠気となって現れるのです。また、たとえ推奨される睡眠時間をとっていたとしても、睡眠の質が低い場合、十分な休息が得られません。
睡眠負債の蓄積は単なる疲労感だけでなく、認知機能の低下や免疫力の低下、さらには生活習慣病のリスクを高める要因にもなります。特に日本人は他国と比べて睡眠時間が短く、慢性的な睡眠不足に陥りやすい環境にあるため、意識的に睡眠時間を確保し、睡眠の質を向上させることが重要です。
昼食後の血糖値の変動によるもの
昼食後の血糖値変動は、夕方の眠気を引き起こす重要な要因の一つです。食事により体内に取り込まれた炭水化物は、消化されてブドウ糖として血液中に吸収され、血糖値が上昇します。それに応じて膵臓からインスリンというホルモンが分泌されますが、炭水化物を多く含む食事を摂取した場合、血糖値が急激に上昇し、その後インスリンの働きによって急激に低下する「血糖値スパイク」という現象が起こることがあります。
この血糖値スパイクが問題となるのは、急激な変動そのものが強い眠気やだるさを引き起こすからです。血糖値が高い状態が続くと、覚醒を促す「オレキシン」というホルモンの分泌が抑制され、さらに眠気を感じやすくなります。特に、丼物や麺類などの炭水化物中心の昼食を摂った後や、空腹状態が長く続いた後に食事をすると、この現象が起こりやすくなります。
また、早食いやドカ食いも血糖値の急上昇を招き、その後の急降下により午後の強烈な眠気へとつながるメカニズムが働いています。このような血糖値の乱高下は、単なる生理的な疲労感とは異なり、体内のホルモンバランスの乱れによる症状として現れるため、適切な食事管理が眠気対策の鍵となります。
体温の変動によるもの
夕方の眠気は、私たちの体に備わった自然な体温変動リズムと深く関わっています。人間の体温は24時間単位で変化する概日リズムを持っており、早朝が最も低く、夕方が最も高くなって、夜になると下がり始めます。この体温変化は、午後2時から6時頃に最も高くなり、その後次第に低下していくという特徴があります。
興味深いのは、眠気と深部体温の関係です。眠りに入る時に手足の甲の皮膚血管が開き、手足から外界に熱が逃げていくことで体の内部の温度が下がり、脳温も下がって眠りに入るのです。夕方になると体温が最高値に達した後、夜に向けて下降準備が始まります。この体温低下の準備段階で、体は放熱システムを活性化させ、深部体温を効率的に下げようとします。この生理的な体温調節プロセスが、夕方特有の強い眠気を引き起こしているのです。
さらに、人間の脳は昼間フルに使われており、疲れた脳がオーバーヒートしないように脳の温度を下げて休ませる必要があります。夕方の眠気は、一日酷使された脳が休息を求めているサインでもあり、体温調節システムと連動した自然な現象といえるでしょう。
脳の疲労によるもの
夕方に眠くなる原因として、脳の疲労は重要な要因の一つです。現代社会では、パソコンを使った作業などを長時間続けると、脳が酷使されて情報処理能力がダウンしてしまう状態が起こります。特にIT系の仕事や業務が増えてきていること、テレワークが進んだことによりパソコンで仕事をしている時間が増えたこと、スマホを一日中操作していることが脳疲労の主な原因となっています。
脳疲労のメカニズムは、脳を使いすぎると脳内で炎症を起こし、正常に機能しなくなってしまうことで起こります。脳内には思考を司る大脳新皮質、本能を司る大脳辺縁系、自律神経をコントロールする間脳があり、これらが情報共有しながらバランスよく働いています。しかし、脳が処理できないほど大量の情報が入ってくると、それぞれがキャパオーバーになってしまい、うまく連携が取れず、機能不全となってしまうのです。
この状態が続くと、夕方になると判断力や集中力が著しく低下し、強い眠気として現れます。また、睡眠は昼間に活動した際に消耗した血液や体液を補給する時間ですが、脳疲労により睡眠の質が低下すると、翌日活動するための栄養が十分でないため夕方頃に疲労感と眠気が出現するという悪循環が生まれます。
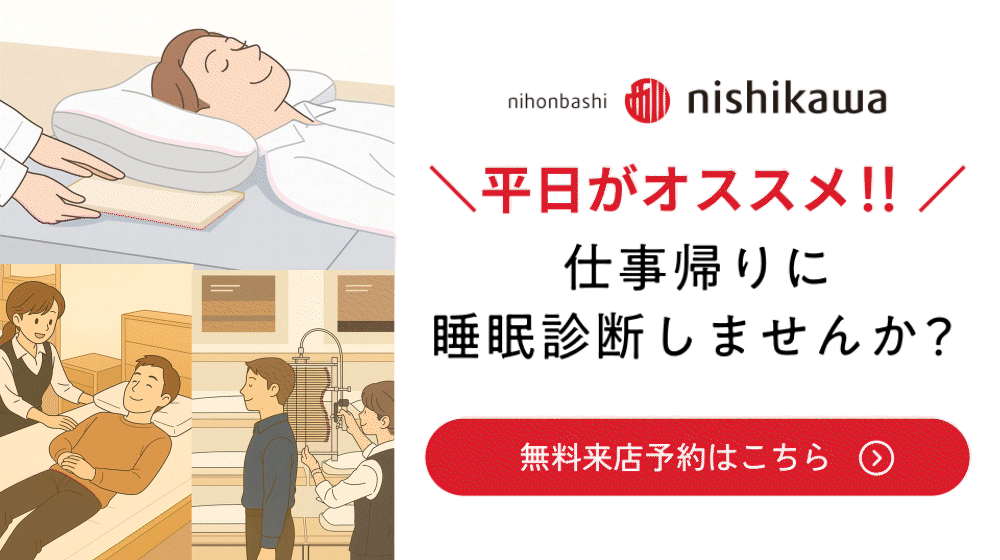
病気の可能性も…
夕方の強い眠気が単なる疲れや生活リズムの乱れではなく、実は病気のサインである可能性もあります。睡眠時無呼吸症候群では、夜間の睡眠中によく目が覚める、起床時の頭痛や体のだるい感じ、日中の眠気などを経験します。この病気は睡眠中に呼吸が止まったり浅くなったりするため、質の良い睡眠が取れず、日中に強い眠気として現れるのです。
また、貧血による眠気は、血液中のヘモグロビンが減少し、体内の酸素を運ぶ能力が低下することで起こります。特に女性に多い鉄欠乏性貧血では、脳への酸素供給が不足し、意識が朦朧とするほどの強い眠気を感じることがあります。生理中や食後に症状が悪化しやすく、単に休息を取るだけでは改善しない特徴があります。
甲状腺機能低下症では、強い倦怠感、疲労感がとれず、日中に強い眠気が出る症状が現れます。この病気は30~40代の女性に多く見られ、甲状腺ホルモンの分泌量が低下することで代謝が悪くなり、慢性的な疲労感と眠気を引き起こします。更年期障害やうつ病と間違われやすく、発見が遅れることも珍しくありません。
さらに、うつ病では過眠症状が現れることがあり、精神的・身体的に疲れ果てているため、過度な眠気や睡眠時間の延長が起こります。この場合の眠気は、ストレスや不安からの逃避として機能することもあり、治療薬の副作用で眠気が強くなるケースもあります。これらの病気による眠気は、生活習慣の改善だけでは根本的な解決が困難なため、適切な医療機関での診断と治療が必要になります。
夕方に寝落ち(夕寝)すると良くないと言われる理由

夕方に寝落ち、いわゆる「夕寝」は、夜の睡眠の質に悪影響を与えるため、一般的には良くないとされています。主な理由は以下の通りです。
夜に眠れなくなる・睡眠の質が低下する
夕方の寝落ちが問題視される最大の理由は、私たちの体内時計と睡眠メカニズムに深刻な影響を与えるからです。夕方以降の昼寝は、夜の睡眠を妨げることにつながります。人の体内時計は約25時間周期で刻まれており、朝の光を浴びることで24時間にリセットされますが、15時以降の夕方に昼寝をしてしまうと、夜間の睡眠への影響が大きくなり、思うように寝付けなくなってしまいます。
夕寝が夜の睡眠の質を低下させる仕組みは「睡眠圧」と関係があります。人は起きている間に睡眠への欲求が蓄積され、これが夜の自然な眠気を生み出しますが、夕方に眠ってしまうとこの睡眠圧が解消されてしまいます。日中しっかりと睡眠をとってしまうと、夜間の不眠につながり、悪循環になりかねません。その結果、本来であれば夜に分泌される睡眠ホルモンのメラトニンのリズムが乱れ、寝つきが悪くなったり、深い睡眠が得られなくなったりしてしまいます。
さらに、太陽の光を浴び、体内時計がリセットされてから15~16時間後にメラトニンが分泌され眠気が生じるように体はできていますが、夕寝によってこの自然なリズムが狂うと、翌朝の目覚めも悪くなり、日中の活動にも支障をきたします。このため、昼寝をするなら午後15時までに20~30分以内に留めることが重要とされているのです。
サーカディアンリズム(概日リズム)が乱れる
夕方の眠気に負けて仮眠を取ることは、私たちの体内時計であるサーカディアンリズムに深刻な影響を与えます。人間の体内時計の周期はそれよりも1時間ほど長い約25時間であることが分かっています。この1時間のずれをリセットするために欠かせないのが朝日です。ところが夕方の仮眠は、この自然な体内時計の調整機能を妨げる要因となってしまいます。
朝の光に含まれる青色のスペクトル成分に、体内時計の針を進め、24時間周期に合わせることを可能にする働きがあるのですが、夕方に眠ってしまうことで夜間の自然な眠気が削がれ、本来の就寝時刻に眠れなくなってしまいます。その結果、翌朝の起床時刻が遅れ、朝日を浴びるタイミングもずれ込むことで、体内時計のリセット機能が正常に働かなくなるのです。
さらに、体内時計には、脳にある「親時計」と全身の隅々の細胞にある「子時計」の2種類があり、親時計と子時計は自律神経やホルモンを介在して連動しています。夕方の仮眠によってこの連動が崩れると、食欲調節ホルモンの分泌異常が起こり、メタボリックシンドロームや糖尿病などの生活習慣病のリスクが高まります。
また、睡眠と覚醒のリズムが不規則になることで、日中の眠気や集中力低下、夜間の不眠といった悪循環が生まれ、心身の健康に長期的な悪影響を及ぼすことになるのです。
起きた後に不快感が残る(睡眠慣性)
夕方の寝落ちが良くないとされる最大の理由は、起きた後に「睡眠慣性」と呼ばれる深刻な不快感が現れることです。睡眠慣性の間、脳と体は正常に機能しません。認知機能の低下、反応速度の低下、判断力の低下、バランスの維持が難しくなるといった症状が現れ、通常15〜30分続きますが、場合によっては2〜4時間も影響が続くことがあります。
30分以上仮眠をとると深い睡眠が出現するため、睡眠慣性が生じやすく、起きた時に頭がボーッとする状態が続きます。この現象は特に夕方の時間帯に深い眠りに入ってしまった場合に顕著で、目が覚めた後も頭がすっきりせず、むしろ眠る前よりも体調が悪くなることがあります。昼寝から覚めてボーッとして、体がだるくて仕方がなく、その後は仕事にならなかったという状態が睡眠慣性であり、昼寝が深過ぎたか長過ぎたかを示すサインです。
さらに、夕方以降の昼寝は夜間の睡眠を妨げるため、翌日の体調にも悪影響を及ぼします。夕方に深い眠りに入ることで体内時計が混乱し、本来の睡眠リズムが狂ってしまうのです。そのため、夕方に強い眠気を感じても、深く長時間眠ることは避け、軽いストレッチや体を動かすなどの方法で眠気を解消することが推奨されています。
意識が飛ぶほど眠い…眠気がひどいときの対処法

夕方にひどい眠気に襲われたとき、夜の睡眠に悪影響を与えずに乗り切るための対処法はいくつかあります。
立ち上がって歩く・軽い運動をする
体を動かすことは眠気覚ましに最も効果的な方法の一つです。座りっぱなしの状態では血流が滞り、脳への酸素供給も不十分になりがちですが、立ち上がって歩くことで全身の血液循環が改善され、脳が活性化されます。軽いストレッチや肩回し、首の運動なども有効で、デスクワーク中でも手軽にできる方法です。
階段の上り下りや廊下を歩くだけでも、交感神経が刺激され、眠気を覚ます効果があります。運動によって体温が上がり、心拍数も増加するため、自然と覚醒状態に移行できます。
外の空気を吸い、光を浴びる
光は体内時計を調整する最も重要な要素の一つです。特に自然光には覚醒を促す効果があり、眠気を感じたときに屋外に出て光を浴びることで、メラトニンの分泌が抑制され、脳が「昼間の活動時間」であることを認識します。新鮮な空気を吸うことで酸素を十分に取り込むことができ、脳の機能を活性化させる効果もあります。
室内でも窓際に移動して日光を浴びたり、深呼吸をしたりするだけでも効果的です。光の刺激は視神経を通じて脳に直接作用するため、即効性が期待できる方法です。
冷たい水で顔や手を洗う
冷たい刺激は交感神経を活性化させ、眠気を一気に覚ます効果があります。特に手のひらを冷やすことは効果的で、手のひらには多くの血管が集中しているため、冷たい水で洗うことで全身の血流が刺激されます。顔を洗うことで、顔面の神経も刺激され、脳への覚醒信号が送られます。
洗面所に行けない環境であれば、冷たいペットボトルや水筒を手に持ったり、首筋に当てたりするだけでも同様の効果が得られます。この方法は即効性があり、気分もリフレッシュできるため、眠気対策として非常に実用的です。
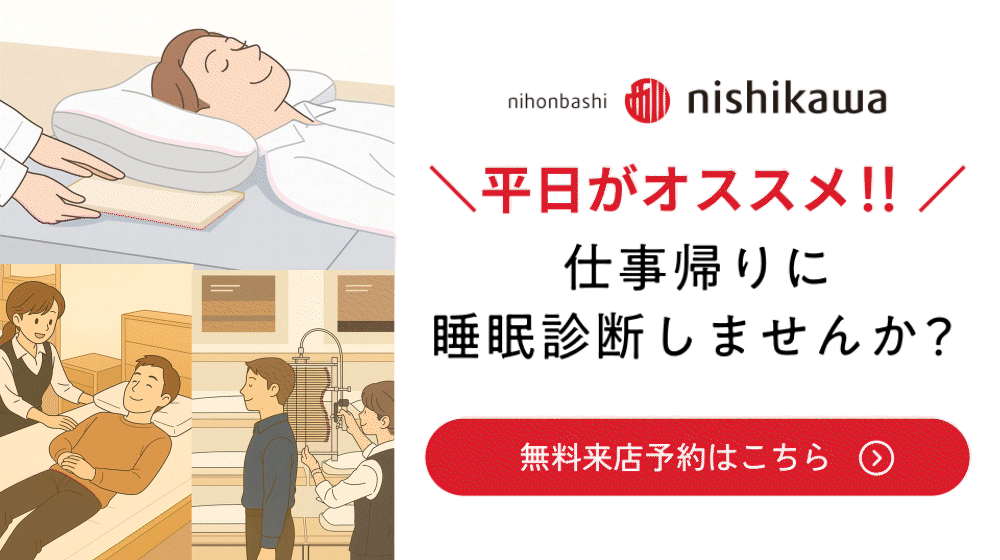
誰かと話す
会話は脳の複数の領域を同時に活性化させる複雑な行為です。相手の話を聞き、理解し、適切な返答を考えるプロセスで、前頭前野をはじめとする脳の広い範囲が働きます。眠気を感じているときでも、会話を始めることで自然と意識がはっきりし、眠気が飛ぶことがよくあります。
特に笑いを伴う楽しい会話は、エンドルフィンの分泌を促し、気分も向上させます。職場であれば同僚との軽い雑談、家庭であれば家族との会話など、短時間でも人とコミュニケーションを取ることで効果的に眠気を解消できます。
ガムを噛む・冷たい飲み物を飲む
咀嚼運動は脳への刺激として非常に効果的です。ガムを噛むことで顎の筋肉が動き、その刺激が三叉神経を通じて脳幹に伝わり、覚醒系の神経を活性化させます。ミント系のガムであれば、清涼感による刺激も加わり、より強い覚醒効果が期待できます。冷たい飲み物も同様に、口腔内の温度変化が神経を刺激し、眠気を覚ます効果があります。
氷を含んだり、冷たい水をゆっくり飲んだりすることで、体の内側から刺激を与えることができます。これらの方法は手軽で、会議中や授業中でも実践しやすい利点があります。
「15分仮眠」をとる
短時間の仮眠は、眠気対策として科学的に効果が実証されている方法です。15分程度の仮眠であれば、深い睡眠段階に入る前に目覚めることができ、起床後の不快感(睡眠慣性)を避けながら、脳の疲労を回復させることができます。
この時間であればノンレム睡眠の浅い段階で留まるため、目覚めた後はすっきりと覚醒し、その後の作業効率が向上します。仮眠前にカフェインを摂取しておくと、目覚める頃にカフェインの効果が現れ、よりスムーズに覚醒できます。
ただし、午後3時以降の仮眠は夜の睡眠に影響するため、時間帯に注意が必要です。椅子に座ったままや机に伏せる程度の軽い仮眠で十分効果が得られます。
関連記事:パワーナップとは?効果やメリット、昼寝が気持ちいい理由を解説
睡眠に関する悩みごとは「ねむりの相談所」へ
眠りに不満を感じている人におすすめなのが、日本橋西川の「ねむりの相談所」です。睡眠科学の専門研修を修了した「スリープマスター」が、活動量計や寝室チェックシステムであなたの睡眠状態を計測・可視化し、一人ひとりにフィットした上質な睡眠環境をご提案します。従来の寝具選びとは異なり、光や音、香りなどさまざまなツールを使って、寝室環境から睡眠習慣まで総合的にアドバイス。あなたの眠りを数値で見える化し、理想の睡眠環境を実現します。質の高い眠りで、より豊かな毎日を手に入れませんか?













